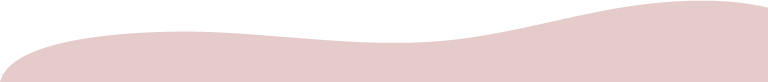目次
1. 鹿屋市で小児訪問看護をお探しの方へ
お子さまに医療的なケアが必要になったとき、「家でちゃんと看てもらえるのかな」「病院まで通うのはちょっと大変…」と不安になる方も多いと思います。そんなときに頼れるのが小児訪問看護です。
鹿屋市でも、医療的ケアが必要なお子さまは少しずつ増えていて、それに合わせて訪問看護のニーズも高まってきています。
この記事では、小児訪問看護ってそもそも何なの?という基本から、選ぶときのポイント、地域との連携のこと、そして鹿屋市での取り組みについて、なるべくわかりやすくお伝えします。
2. 小児訪問看護とは?

小児訪問看護とは、医療的なケアが必要なお子さまのご家庭に看護師さんなどが訪問し、ケアやサポートを行うサービスのことです。病院じゃなく、おうちで安心して生活できるように支えてくれるのが大きな特徴です。
対象となるお子さま
- 医療的ケアが継続して必要な小児(例:人工呼吸器、胃ろう、たんの吸引など)
- 発達支援やリハビリを必要とするお子さま
- 先天性疾患や難病などにより生活に支援が必要な子ども
- 重症心身障害児
- リハビリが必要な未熟児、早産児、多胎児
実際に、鹿屋市でも未熟児や早産児、多胎児で、継続的なリハビリや見守りが必要なお子さまの利用が増えており、医療的ケアとあわせて生活支援のニーズも高まっています。
主なサービス内容
- 健康チェック(バイタル測定)
- 医療的ケア(吸引、注入、呼吸器管理など)
- 日常生活の介助や指導
- ご家族へのサポート・相談
3. 小児訪問看護の選び方のポイント

いざ探そうと思っても、何を基準に選べばいいのか…迷いますよね。そんな時は以下のようなポイントを意識してみてください。
小児専門の経験があるか
子どものケアは、大人とは違う知識や対応力が必要になります。年齢や発達段階に応じた関わり方ができるスタッフがいるかどうかは、大事なポイントです。
ご家族との連携体制が整っているか
訪問看護は、子どもだけでなく家族みんなの安心感が大切です。看護師さんが相談しやすい雰囲気を作ってくれたり、柔軟に対応してくれるかも、選ぶときのポイントです。
医療・福祉との連携があるか
医療機関や福祉施設、保育園などとしっかり連携しているかもチェックしたいところです。スムーズに情報を共有してくれることで、万が一のときにも対応が早くなります。
4. 小児に特化した訪問看護の魅力と重要性
小児専門の訪問看護は、お子さま一人ひとりの成長に合わせたきめ細やかなサポートが魅力です。
- 小児看護の経験があるスタッフが対応してくれる
- 年齢や発達に応じたケアプランを立ててくれる
- ご家族の不安や悩みにも寄り添う
- 子どもとの信頼関係を丁寧に築いてくれる
「ただケアするだけじゃなくて、一緒に成長を見守ってくれる」そんな関係性が築けるのも、小児専門ならではの良さです。
5. 連携体制があると安心な理由
訪問看護は単独ではなく、いろんな機関と協力し合って初めて、より良い支援が実現します。

たとえば…
- 保育園や放課後等デイサービスとの情報共有
- 医療・生活・発達のサポートを一体的に行うー
- 保護者の「誰に相談すればいいかわからない」がなくなる
こうした地域連携があることで、保護者の方の負担もグッと軽くなるんです。
6. 鹿屋市における小児訪問看護の現状と課題
医療の進歩とともに、在宅で医療的ケアを必要とする子どもたちの数は年々増加しています。鹿屋市においても、小児訪問看護のニーズは高まりつつありますが、その一方で支援が行き届かない家庭も少なくありません。(出典:医療的ケア児とその家族の生活実態調査 報告)
現在の主な課題
- 通院が難しい家庭の増加
- 支援制度や地域資源の情報不足
- 医療・福祉の担い手不足
働きながら子育てをしている家庭や、交通アクセスが限られた地域に住んでいる場合、定期的な通院自体が大きな負担となります。特に、小さな子どもを連れて長時間の移動をするのは心身ともに大変で、「本当は診てもらいたいのに、行けない」という声も少なくありません。
実際には利用できる制度やサービスがあっても、「どこに相談すればいいのか分からない」「自分たちが対象になるのか不安」といった理由で、支援にたどり着けないケースも見られます。
小児の訪問看護に対応できる看護師さんや専門スタッフがまだまだ少ないのが現状です。。特に、鹿屋市のような地方では、都市部に比べて人材の確保が難しく、どうしてもサービスの提供に偏りが出てしまうこともあるようです。
地域連携による期待と今後の方向性
- 病院との連携による在宅医療の強化
- 保育・療育施設との繋がりの強化
- 訪問看護の専門性向上と普及
在宅療養をより安心して続けられるようにするためには、医師との密な連携が欠かせません。指示書の整備や緊急時の連絡体制を強化することで、訪問看護の現場でもより的確な対応が可能になります。
子どもたちは家だけじゃなく、保育園や療育の場でもたくさんの時間を過ごします。だからこそ、そこにいる先生たちともしっかりと情報をやり取りできるように、訪問看護が“つなぎ役”としてうまく動けると、子どもの日常がもっと安全で、心地いいものになるはずです。
どうしても訪問看護って「お年寄りのためのもの」って思われがちですが、実は小さなお子さまにもすごく大事な支援です。ですがそのことを知らない人が多いのが現実。だからこそ、もっと広く知ってもらうこと、そしてそのケアをできる人を育てていくことも、これからの大事な課題のひとつです。
7. 訪問看護ステーション結の取り組み
訪問看護ステーション結では、小児訪問看護に力を入れ、地域のご家庭とともに成長を見守る体制を整えています。
- 小児経験豊富な看護師が在籍
- 理学療法士との連携で発達支援も対応
- ご家族との定期的な面談とフォロー
- 対応エリア:西原、今坂、郷之原町、大浦町、上谷など鹿屋市一円
8. Just a Littleとの連携について
訪問看護ステーション結は、関連法人「Just a Little」と連携し、医療・福祉・保育がシームレスにつながる体制を実現しています。
Just a Littleで提供されるサービス

- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 単独型短期入所
- 保育園
発達に不安がある未就学児のお子さまを対象に、日々の生活の中で「できること」を少しずつ増やしていくための支援を行っています。遊びや日常生活の動作を通じて、身体の動かし方、コミュニケーションの取り方、集団生活への慣れなど、個々の発達段階に合わせたプログラムが用意されています。
小学生から高校生までの子どもたちが、放課後や長期休暇中に安心して過ごせる居場所です。学習支援や創作活動、社会性を育むためのグループワークなどを通じて、将来の自立に向けたサポートを行っています。
ご家族の一時的な休息(レスパイト)や、急な用事があるときなどに、お子さまを短期間お預かりするサービスです。医療的ケアが必要なお子さまも、専門スタッフが常駐する安心の環境で、安全に過ごせるよう配慮されています。
日々の保育の中にも、医療や福祉的な視点が自然に組み込まれているのがJust a Littleの保育園の特徴です。医療的ケアが必要なお子さまでも、専門スタッフと看護師が連携することで「みんなと一緒に過ごせる」環境を実現しています。
このような支援体制により、お子さまの「日常生活」と「医療的ケア」の両方をサポートできる環境が整っており、ご家庭にも大きな安心感を提供しています。
9. ご家庭の声と1日の訪問スケジュール例
-

(30代/4歳男児の母)
「4歳の息子は言葉が少ないんですが、結の看護師さんにはすごく心を開いていて。遊びの中でケアしてくれるから、本人も負担に感じていないみたいです。」

(40代/6歳女児の父)
「私はひとり親で、平日はどうしても仕事を休めないことが多いんです。でも、保育園と連携して看護師さんがフォローしてくれるので、本当に助かっています。」

(20代/3歳女児の母)
「初めての育児でわからないことだらけでしたが、訪問看護の方が定期的に来てくれて、小さな変化にも気づいてくれるのでとても心強いです。」
1日の訪問スケジュール例(ご家庭での流れ)

- 9:00頃|訪問前の準備
- 9:30|看護師訪問開始
- 9:35|前回訪問からの経過確認
- 9:40|バイタルサイン測定
- 9:50|医療的ケアの実施
- 10:00|入浴または清拭
- 10:30|リハビリテーションや発達支援
- 10:45|ご家族へのサポート・相談
- 11:00|看護師退室
ご家族が体温や体調の様子を確認し、必要な医療機器やケア用品を準備します。
看護師が訪問し、ご家族と挨拶を交わしながら、お子さまの様子を観察します。
ご家族から、お子さまの体調や生活の変化について聞き取りを行い、必要な情報を共有します。
体温、脈拍、呼吸数、血圧、酸素飽和度などを測定し、現在の健康状態を評価します。
必要に応じて、吸引、経管栄養、呼吸器管理、排便ケアなどの医療的ケアを行います。
お子さまの体調が良好であれば、入浴の介助を行います。入浴が難しい場合は、清拭で清潔を保ちます。
理学療法士や作業療法士と連携し、運動機能や日常生活動作の向上を目指したリハビリを実施します。
ケアの方法についてのアドバイスや、育児に関する相談を受け、ご家族の不安や疑問を解消します。
看護師が退室し、その後はご家族とお子さまでゆったりと過ごす時間となります。
※上記のスケジュールは一例であり、お子さまの状態やご家庭の希望により、内容や時間は柔軟に調整されます。
10. ご利用の流れと費用
- お問い合わせ・ご相談
- 医師からの訪問看護指示書の発行
- ご家庭との面談・契約
- サービス開始
まずはお電話やメールでお気軽にご連絡ください。お子さまのご様子やご家庭の状況を伺い、訪問看護の内容について丁寧にご案内します。お問い合わせはこちらから
訪問看護を行うには、主治医からの指示書が必要です。ご相談後、必要に応じて主治医と連携を取り、指示書の発行を依頼します。
実際のサービス開始前にご家庭を訪問し、お子さまの状態やご希望を確認します。その後、正式に契約を結び、訪問スケジュールやケア内容の調整を行います。
スケジュールに沿って訪問看護がスタートします。看護師は、お子さまやご家族に寄り添いながら、日々のケアをサポートしていきます。
費用について
訪問看護は健康保険の対象サービスです。多くの小児(18歳未満)は、以下の公的制度によって自己負担が軽減されます。
- 乳幼児医療費助成制度(自治体により名称や条件が異なります)
- 重度心身障害児(者)医療費助成制度
- 自立支援医療制度(育成医療) 等
これらの制度を利用することで、安心してサービスをご利用いただけます。
※制度の内容や適用条件は地域やご家庭の状況によって異なります。個別の確認や手続きのサポートも行っておりますので、ご不明な点は遠慮なくご相談ください。
(参考文献:
https://www.pref.kagoshima.jp/ae08/kenko-fukushi/kodomo/teate/documents/4214_20250327201315-1.pdf
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/fukushi/syofuku/documents/03tebiki.pdf
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kosodate/boshihoken/kosodate/ninshin/teate/jiritsu/index.html)
11. よくある質問(Q&A)
- Q. どんな子どもが訪問看護の対象になりますか?
- Q. 家ではどんなことをしてくれるんですか?
- Q. 保護者が在宅していないとサービスは受けられませんか?
- Q. 保育園や福祉施設と連携してもらえるのでしょうか?
A. 医療的なサポートが必要な子はもちろん、退院後の体調管理が不安なお子さんなど、幅広く対応しています。
A. 吸引や注入、バイタルチェックのほか、ご家族へのケアのアドバイスや相談も行っています。
A. 状況に応じて柔軟に対応しています。安全面やお子さまの状態をふまえて個別に調整しますので、まずはご相談ください。
A. はい。園や施設との情報共有や連携も積極的に行っており、日常のケアがよりスムーズになるようサポートしています。
12. まとめ|子どもの未来を支える地域連携型の小児訪問看護

小児訪問看護は、病気や障がいのあるお子さまが、その子らしく、安心して日々を過ごすための大切なサポートです。単に医療的ケアを届けるだけではなく、ご家族の気持ちに寄り添いながら、子どもの成長を一緒に見守っていく存在でもあります。
訪問看護ステーション結では、お子さま一人ひとりのペースや個性に合わせた丁寧な看護を心がけ、ご家庭とチームを組んで寄り添うケアを大切にしています。日々の中でのちょっとした不安や悩み、誰に聞けばいいかわからないことも、どうぞ気軽にご相談ください。
子どもたちが住み慣れた場所で笑顔を育み、未来へ一歩ずつ進んでいけるように。私たちはこれからも、地域とつながりながら、その歩みをそっと支えていきます。
(出典:https://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-20181219/dl/after-service-20181219_houkoku.pdf)